法名(ほうみょう)とは

真宗大谷派では、仏弟子となられた証として授かるお名前を「法名」と呼びます。法名はお釈迦様の弟子として生きていくことを誓う名であるため、本来は生前に帰敬式(ききょうしき)を受けていただくものですが、現在ではお亡くなりになった際に授かることが多くなっています。
法名の付け方には全国で統一された厳密な決まりはなく、各寺院の考え方によって様々です。
真宗大谷派の法名
一般(普通)法名
男性の法名:釋〇〇(しゃく〇〇)
女性の法名:釋尼〇〇(しゃくに〇〇)
院号法名(いんごうほうみょう)
院号法名:〇〇院釋(尼)〇〇
このように、真宗大谷派の法名は、一般的な法名と院号法名に大別されます。どちらの場合も、女性には「釋」のあとに「尼」の字が入ります。
法名の読み方について
法名は、基本的に漢字を音読みします。音読みには呉音(ごおん)・漢音(かんおん)・唐音(とうおん)などがありますが、仏教用語では古く伝わった「呉音」で読むのが慣例です。
呉音(ごおん):古く日本に入った漢字音の一。もと、和音とよばれていたが、平安中期以後、呉音ともよばれるようになった。北方系の漢音に対して南方系であるといわれる。仏教関係の語などに多く用いられる。
デジタル大辞泉引用
例えば「明」という字の呉音は「ミョウ」、漢音は「メイ」、唐音は「ミン」となります。
ここでは呉音の詳しい説明は省きます。もしお付き合いのあるお寺があれば、法名の読み方を直接お尋ねになるのが確実でしょう。当寺でも皆様から読み方についてのご質問が多いため、葬儀の際にお渡しする資料に法名の読み方(ふりがな)を記載しています。また当寺では難しい字や読みにくい字はなるべく使用せず、どなたにも親しみやすい漢字を取り入れるようにしています。
当寺における法名の考え方
ここからは、あくまで当寺における法名の付け方と考え方についてご説明します。
お名前(俗名)から一字をいただく
法名の「〇〇」の二文字には、ご遺族からご希望の漢字をいただくことも可能です。特にご希望がない場合や当寺にお任せいただく際には、故人様のお名前(俗名)から一字をいただくことを基本としています。
例えば、「花子」様というお名前であれば、お名前の頭文字である「花」の字をいただく、といった具合です。 当寺がお名前から一字をいただくのは、その方のお名前こそが、その方の人生そのものを表していると考えるからです。お名前には、ご両親の「このように育ってほしい」という願いが込められています。その尊い人生に敬意を表し、お名前の一字を法名に用いさせていただいております。
もう一字に用いる漢字
お名前からいただいた一字に、もう一字を添えて法名とします。この一字には、仏教の教えに由来する漢字などを中心に選ばせていただきます。 これも当寺の考え方ではありますが、男性・女性それぞれの響きやイメージを大切に、以下のような漢字を用いることが多くあります。
男性に用いることが多い漢字の例
・照(しょう)
・浄(じょう)
・徳(とく)
・道(どう)
・願(がん)
女性に用いることが多い漢字の例
・清(しょう)
・香(こう)
・妙(みょう)
・華(げ)
昨今、男女を明確に区別することへのご意見があることは承知しております。その上で、漢字が持つ「響きの美しさ」や「柔らかな印象」「実直な印象」といった特性を大切にしたいと考えております。
院号に用いる文字
院号法名をお付けする場合、「〇〇院」の部分には、故人様のお人柄やご趣味、お好きだったものなどを伺い、その生涯を象徴するような文字を選ばせていただいております。
まとめ
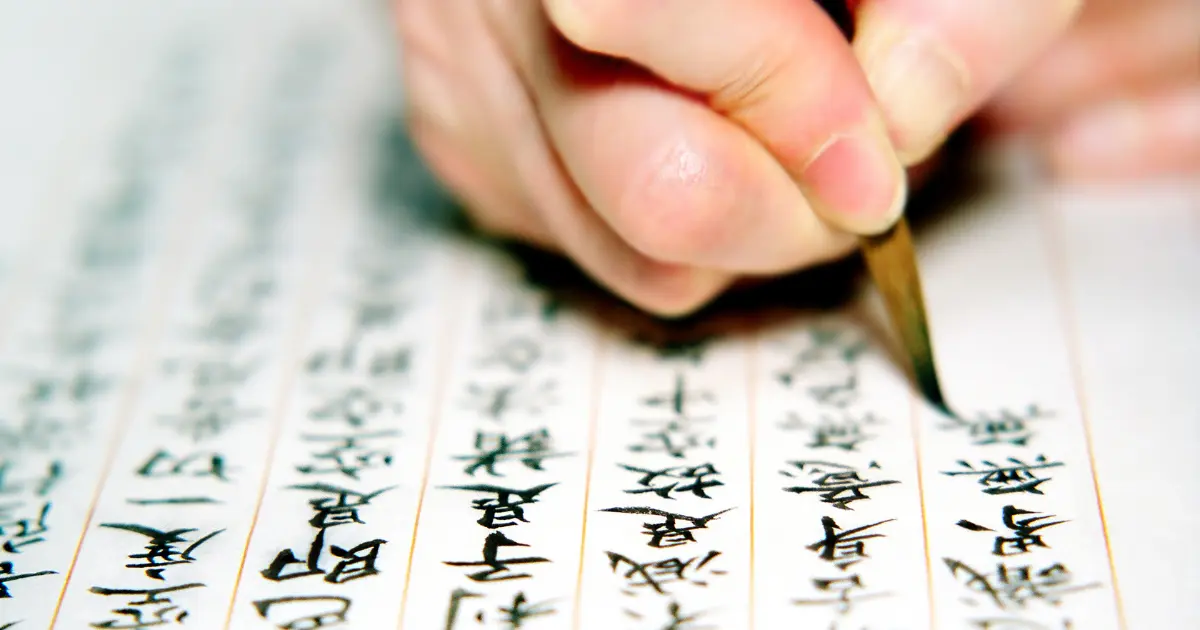
法名の付け方に、全国で統一された厳密なルールはありません。そのため、ご不明な点やご相談は、菩提寺(お付き合いのあるお寺様)にお尋ねになるのが最も良い方法です。法名の読み方はもちろん、その文字が選ばれた理由なども、きっと快く教えてくださることでしょう。
もちろん当寺でも、法名に関するご質問やご相談はいつでもお受けしておりますので、どうぞお気軽にお声がけください。
【参照】



